 |
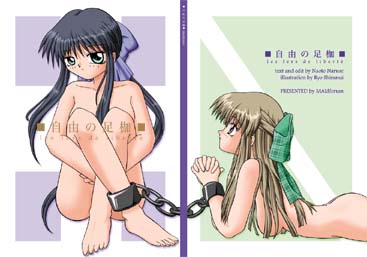
|
||
| 「自由の足枷」 | |||
B5/78ページ 表紙 カラー/本文 スミ1色 「Kanon (key)」川澄 舞の小説 text and edit by 成瀬 尚登 / illustration by 不知火 菱 即売会価格 500円/一般向 [履歴] 2002年12月30日(Comic Market63) 発行 |
|||
|
【本文紹介】 プロローグ 剣先を翻して、ためらいなく水平に引く。 青い光がきらめいて闇に線を描き、空気がなびいて風のように揺れる。 激烈な咆吼が、鼓膜を震わせる。それでも、突進は止まらない。巻き込まれないように後方へ跳び、すぐに背後へ向き直って剣を構えなおす。 深い藍色の闇。雲に紛れた月光が窓から射し込み、リノリウムの廊下をぼんやりと照らしている。 何もない。そこには何も見えない。 だが、今にも破裂しそうな緊張感は残っている。 たしかに手応えはあった。ずきっという手首の鈍痛がその証拠だ。 それはすれ違いざまに表面をえぐられながらも、そのまま横を抜けていき、そして姿を消した。 かすかな月光に剣を浸しながら、剣先に神経を渡らせ、気配を探っていく。 すると、いきなり、肌が引き攣れるほどの強烈な存在を、廊下の奥で感じた。 視線だけ、移す。 腹部に一条の痕。 腐った緑色の苔むした影をまとって、それは、ふたたび姿を現した。 すさまじい殺気が、闇をこえて伝わってくる。 静かに、それと対峙した。 剣を持つ手首に力を込め、下段に構える。 それが、合図となった。 まっすぐこちらに駆けてくる、それの動き。 合わせて宙に跳躍し、振りかぶって剣を叩きつける。 寸前で交わされ、剣先はそれの表面をわずかにかすった。 着地して反転し、間髪入れず跳びかかる。 刹那、背後の窓から射し込む光が強くなり、澱んだ緑の輪郭が輝く。 その輝きへ向けて、剣を振り下ろした。 剣の軌跡は、それの躯の真芯を貫くように描かれていく。 不気味な感触が手首に伝わる。 だが、その瞬間、軌跡が歪んだ。 左に逸れ、剣はそれの躯を深くえぐっただけだった。 虚を突かれ、次の一撃への反応が遅れる。 その隙をついて、それは窓へ向けて飛び上がった。 破裂音が響き、ガラス窓にいびつな形の穴が開いた。 それを追って窓のそばに駆け寄り、外を見やった。 裏庭に屹立する木の白い影、厚く積もった雪は無垢なまま時を留めていた。 荒涼とした冷たい風が頬に吹き付ける。吐く息が白く霧散していく。 その時、右手首が疼いていることに気づいた。 最初の一太刀で痛めた右手首がじんじんと痛み出してきた。それが仕留めそこなった理由だ。 不意に、無力感が心に浮かんできた。 今夜もまた無為な時を過ごしてしまった。 終わるのか。 いつまで続くのか。 外からの風が急に強くなる。 風切り音が、不可解な音階を奏ではじめる。 そして、いきなり突風が吹き込んできた。 その風で、ひびの入っていた部分が、風に押し込まれて砕け散った。 とっさに腕で顔を隠す。 「……くっ」 破片は頭や身体に降り懸かって、床に散乱した。 身構えた。だが、気配はない。 ひとつ深く息を吐いて、剣を下ろし、廊下を歩き出した。 風は雲を呼び込み、月は輝きをその向こうに隠していた。 闇がまた世界を満たす。 わずかに右頬に痛みを感じた。 左手の薬指を当て、そのまま目の前に掲げると、そこには血がにじんでいた。 「……困らせてしまうかな」 窓から吹き込む不思議な音階は、やがて、丘陵の針葉樹のざわめきまでをも運んできていた。 第1章 1 朝靄が陽光にきらめいていた。 冬の空は明けたばかりで、端には赤みが残っている。そこから緩やかに極を描きながら、冴えた青へと、その色を変えていく。 ころころと乾いた音をたて、川が流れている。水量は乏しいながらも、湧き上がる水蒸気の粒ひとつひとつが、やわらかい光に照らされて輝いている。 その川縁の歩道を、今朝はひとりで歩いていた。いつもよりも早い時間だ。同じように川縁を歩いて学校へ向かう生徒たちの数もまだ少ない。 冷たい風が頬を抜ける。右手を右の頬に寄せ、指で撫でた。 小さな絆創膏が貼られている。 女の子なんだから、顔の傷には気をつけないとだめだよ。 そう言った彼女の言葉が思い出される。 その時、とたとたという足音が背後から迫ってきた。 その足音に、振り返らず、歩くペースだけを落とす。 足音は、すぐ横で止まった。 「……ふう、追いついた」 ちらりと横を向く。 そこにはよく知っている少女がいて、目が合うと、にっこりと微笑みかけてきた。 同じ学校の制服、同じ学年の胸のリボン。長い髪を両脇からまとめるように緩やかに束ね、チェックの幅広のリボンで結っている。 そして、華やかな雰囲気を振りまく、晴れやかな笑み。 鞄と、いつものように風呂敷包みを提げている。 「……ゆっくり来てもいいのに」 「おいていくなんて、ひどいよ」 その右側に、彼女は寄り添うようについてくる。これで、いつもの日常に戻った。 「遅くなってごめんなさい」 「私が早いだけ……」 すると、彼女はおのずと納得した顔をしてうなずいた。 知っている。そう、彼女は知っている。どうして今日は早く家を出たのかを。すっかり見透かしているのに、それでいて、何も言わないでいる。すこしだけバツの悪さを感じた。 「間に合ってよかった。今日のお弁当はちょっと手間がかかるものだったから」 そう言って、風呂敷包みを掲げる。 「喜んでもらえるといいな」 彼女はまたにっこりと微笑む。 喜ばないはずはない。 だから、ひとつこくんとうなずいた。 そうして、とりとめのない話しをしながら歩いていく。 やがて、学校の正門が見えてきた。門の前には腕章をした生徒が立っている。 「……佐祐理、先に行ってて」 そう言い残して、ひとり早足で先に行こうとする。 その時、後ろから声がかけられた。 「早く濡れ衣が晴れるといいね」 振り返ると、純粋で無垢な笑みがそこにあった。こくんとうなずいて、また足を進めた。 † 生徒会室を退出すると、廊下には佐祐理の姿があった。 「お疲れさま」 晴れやかな笑顔で迎えてくれる。 時間にして、授業のはじまるほんのすこし前だ。 「どう、濡れ衣は晴れた?」 その問いに、首を縦にも横にも振れなかった。 生徒会に召喚された理由、それは、旧校舎における昨夜のガラス破損についてだった。それも今回が初めてではない。 旧校舎で夜更けに剣を振り回しているという事実は、伝聞による噂として校内に流布されていた。そのため、旧校舎の器物が毀損されるたびに生徒会に召喚されていた。今回も疑われて当然ではあった。だから、自分が原因ではなかったが、たぶん呼ばれるだろうという予感があって、それで早く家を出たのだった。 しかし、今回のガラスの破片の飛び散り方は異常だった。廊下にガラスが散乱しているということは、何かが外から飛び込んできたことを意味するが、その何かは旧校舎に残っていない。 結局、日頃の素行に対する戒告が、具体的な事件とは離れて、あくまで形式的になされただけだった。 濡れ衣は晴れたという問いに、肯定も否定もできない。 並んで廊下を歩き出した。 歩いている最中も、隣りにいる佐祐理の表情を見られなかった。自分を心配してくれる佐祐理の顔を見るのが、ただ無性につらかった。 「ところで、今朝、説明し忘れていたことがあったの」 視線を向ける。 「今日はウィンナーをたくさん茹でてきたから、たくさん食べてね。それで……」 指を伸ばして、右の頬を撫でる。 絆創膏の貼られたところだ。 「これも、お弁当のときに貼り替えようね」 「……うん」 その時ばかりは、口に出して、そう答えた。 2 リノリウムの廊下に青い光が反射して、世界がにじんで見える。 割れてしまったはずのガラス窓はすでに交換されていた。 まるで昨夜の光景だ。それをふたたび見ているだけに過ぎないような錯覚があった。 それの気配は、まだ感じられない。急所を外したとはいえ、手負いにはしている。現れれば、確実に仕留められるはずだ。 剣を握る右手首に力を込めた。じゅくっという痛みが浸みる。追って、佐祐理に貼ってもらった湿布の熱さが広がっていく。 佐祐理は頬の傷を見つけると、優しく絆創膏を貼ってくれた。ただ一言、女の子なのだから顔には気をつけないと、と。それだけではなく、手首の腫れにも気づいて、そこにも湿布を貼ってくれたのだった。 右手首をじっと見つめ、そっと左手をそこに添えた。 その時、いきなり、強烈な気配が総身を貫いた。 うかつさに愕然としながらも、反射的に身を退いて、剣を構える。 20メートルほど先、そこには同じくらいの年齢の少年の姿があった。 「や、やあ……」 夢でも見ているかのような、まるで信じられないといった顔。 なおも警戒を解かず、鋭い瞳を向ける。 少年の顔が焦りに変わった。 「べ、別に怪しい者じゃないぞ。忘れ物を取りに来ただけだ」 そう言って、手にしていたノートを大きく振る。 気配を探っていく。一つだけ、この少年のものだけだ。 どこか釈然としないものを感じながらも、構えを解いて視線を逸らせた。それは、この場を離れるよう、少年にうながそうとしてのことだった。 しかし、少年の気配は去らなかった。 視線を向けると、興味深く自分に向いている目があった。 「何か、待っているのか?」 ぶしつけな問いかけだ。けれども、そこには冷ややかな侮蔑の色はない。 純粋に何かを理解したいという気持ちが目にあらわれていた。 「こんな夜更けに、ひとりでいるなんて、何か理由があるんだろう」 答える代わりに、少年に背を向けようとした。 言葉にならない理由があるだけで、言葉にしてそれに答えられる術はないのだから。 だが、次の瞬間、それを思いとどまって、剣を構えなおした。 それは、醜い輝きをもって、少年の背後に密やかに浮かび上がりつつあった。 「逃げて……」 とっさに口にして、駆け出す。 「うわっ!」 剣先を向けられた形の少年は、避けるように廊下にへたりこむ。 醜い輝きはリノリウムの廊下に完全にその影を映し出すと、床に座り込んだ少年をめがけて突進してきた。 「ぐぁっ!」 側面からそれをまともに受け、少年は投げ出されて倒れ込んだ。 醜い輝きをもつそれは、その衝撃で動きを鈍らせる。 その隙を見逃さなかった。 跳躍する。 そして、体中の力を込め、剣を叩きつける。 剣は垂直に体内に刻まれていき、一気に躯の深いところまでを裂いた。 咆吼がとどろく。 同時に、その反動のせいか、剣を繰り出した自分の脇腹にも痛みが走る。 それをこらえ、さらに致命的な打撃を繰り出そうと、剣を力任せに引き抜いた。 しかし、今度は逆にその隙をつかれた。わずかな間合いから、それは廊下の奥へと駆け出した。 追おうとするも、脇腹に痛みが走り、足に力が入らない。 廊下の闇の中へ消えていくのを、ただ憮然として見届けるしかなかった。 「……ッつう……」 少年の声。壁に手をつきながら、よろよろと立ち上がった。 「なんだ、今のは」 「……魔物」 観念して、そう答えた。 醜い輝きを放ち、この場所を徘徊するそれを、いつからか魔物と呼んでいた。 魔物は、自分だけにしか見えない。それを形容する適切な言葉を知らない。 だから、決まって、魔物という言葉を聞いた者は、いぶかしげな顔、疑わしげで冷ややかな視線を向ける。 もう、それにも慣れてしまっていた。 「魔物……?」 「私は……魔物を討つものだから」 つぶやくようにそう言って、少年に背を向け、消えてしまった魔物の気配をふたたび探ってみる。 昨夜に続いて、昨夜以上に傷を負わせた。今夜また出てくれば、初めて仕留めることができる絶好の好機となるはずだった。 しばらくそうしてみて、やがて深く溜息をつき、肩の力を抜いた。 消えたきり、魔物の気配は完全に消失してしまっていた。 手負いであるからこそ、今日は姿を現すまい。魔物は愚かではない。 そう結論づけて、振り返った。 少年は、落としたノートを拾い上げていた。 身体を起こし、こちらへ顔を向ける。 「がんばれよ」 その顔は、さりげなくにこやかだった。 そのまま背を向けて、廊下の向こうへと歩いていく。 不思議な印象が残った。 純粋な……そう、畏怖や侮蔑、それらをまったく感じさせない瞳が記憶に残った。 少年の影がリノリウムの廊下の闇へ消えていくのを見送る。 そして、虚空を一瞥し、自分もまた歩き出した。 † 朝靄が、川縁を飾っていた。 雪の季節にはめずらしく、快晴が続いた。それでいて空気は冷たく、かすかな吐息ですら濃い乳白色に濁っていく。 今日はいつもどおりの時刻に家を出た。隣りには佐祐理が歩いていて、いつもと同じく、晴れやかな笑みを浮かべていた。 「昨日はぐっと冷え込んだね。寒くなかった?」 首を横に振る。昨日は家に戻ると、ベッドには毛布がもう一枚ほど用意されていた。 「これからもっと寒くなるから、欲しかったら、また言ってね」 「うん」 その時、不意に、後ろから駆け足が聞こえてきた。それは、すぐ後ろで止まった。 「よお……」 足を止め、振り返る。 「ああ、やっぱりそうだったか。見つけたぞ」 同じ学校の制服を着た少年が、息を切らせながら、そこに立っていた。 何の感動もなく、その表情をながめる。 少年は急にむっとした顔を見せた。 「なんだ、もう忘れたのか」 覚えている。昨夜、廊下で遭った少年だ。 同じ気配、同じ声。そのことが当然というように、それらは確実に記憶されている。 少年は憮然として、それ以上何も言おうとしない。 「あの、どなたでしょう?」 すると、隣りにいた佐祐理が、晴れやかな笑顔を少年に向けた。 「あ……」 いきなりの反応に、少年はたじろぐ。 「いや、その……」 文字通り、どぎまぎした表情をする。 佐祐理はこちらを向いた。 「舞のお友だち?」 「昨日会っただけ」 「なんだ、おぼえてるじゃないかっ」 苛立ち混じりの少年の声に、佐祐理は苦笑した。 「舞のお知り合いなんですね。お名前は何というのでしょう」 「あ……祐……一。そう、相沢祐一」 「相沢祐一さんですね。はじめまして、倉田佐祐理と申します……ほら、舞も自己紹介しないと」 「……舞。川澄、舞」 みずからを、そう名乗った。 † 午前の最後の授業が終わった。しばらく授業が延長され、チャイムが鳴ってから3分ほど経過していた。 授業の道具を机にしまって立ち上がる。 「遅くなっちゃったね、舞」 佐祐理が横に並び、教室を出た。 すこし離れた廊下の壁に、祐一が寄りかかっていた。 「祐一さん、早いですねー」 「ああ。チャイムが鳴った瞬間に教室を出て、駆け出してきたから」 「ぴったりに授業が終わるなんて、うらやましいですね」 「いや……」 祐一は苦笑した。 「授業が終わった瞬間……なんて、言ってない」 「あははーっ、だめですよ、祐一さん」 「では、お昼休みに、一緒にお弁当を食べましょう」 佐祐理はいきなりそう言った。 通学路で自己紹介をした後の台詞だ。 「祐一さん、だなんて。佐祐理さんの方が年上なんだから」 苦笑混じりのその答えは、問いに対する答えになっていなかった。 「いいんですよ、呼び捨てにするなんて、佐祐理にはできません」 そして、付け加える。 「佐祐理、でかまいませんから」 「それはちょっと馴れ馴れしすぎるような……佐祐理さん、で、どう?」 佐祐理は微笑みながらうなずいた。 祐一は、続いて舞のことを見る。 「舞でいい」 舞はその機先を制した。 自分は舞なのであって、それ以外のものではない。それ以外の呼ばれ方をすると、自分が自分ではなくなってしまうように思う。 「……わかった、そうする」 「では、午前の授業が終わりましたら、佐祐理たちの教室に来てください」 「明日から、祐一さんの分も作ってきますよ」 屋上へと続く階段の手前の踊り場で、佐祐理と祐一とで昼食を囲んでいる。 風呂敷包みが開かれ、重箱が3つ並べられていた。 佐祐理と舞、二人以外がここにいることは、初めてのことだったと覚えている。 いつも舞の対面には佐祐理がいて、佐祐理は対面の舞にお茶を淹れてくれたり、お弁当を取り分けてくれたりしてくれる。 その佐祐理の視線が、いまは、祐一に向かっている。 やわらかい、ハーブティの薫り。 「こちらこそ、喜んで。でも、このハーブティは青臭くなくていいなあ。おかわり、もらえないかな」 手にしていたカップを佐祐理に差し出すと、佐祐理は嬉しそうにその中に浅黄色の液体を注ぐ。注ぎ終わると、祐一は嬉しそうにそれを引き寄せた。 「ハーブティって臭い感じがするから、ちょっと遠慮していたんだけど、これなら飲める」 「佐祐理は、慣れてますから」 「なんか、すごいや、佐祐理さん」 「そんなことはありませんよ。佐祐理はちょっと頭の悪い普通の女の子ですから」 舞もコップを傾けて中を空けると、佐祐理の前に突き出した。 「はい」 佐祐理がハーブティを注ぐ。 その様子を、祐一は興味深げにながめていた。 「佐祐理さんと舞って、どういう関係なの?」 「え、どうしてですか?」 「お弁当を作ってあげたり、お茶を淹れてあげたり、一緒に学校に来たり」 純粋に知りたいと望む瞳。昨夜のそれと同じだ。 「そうですねー」 佐祐理は小首を傾げ、すこし考えてから、こう答えた。 「佐祐理は、舞のメイドさんなんですよ」 「メイド……?」 そうつぶやきながら、助けを求めるかのように、祐一は舞へ視線を向けた。 「佐祐理は、私のお姉さん」 舞は素直に答えた。 「お姉さん……」 「あははーっ、よけいにわからなくなっちゃってますね、祐一さん」 困惑する祐一と、苦笑する佐祐理。 「だって……本当のことだから」 それっきり、舞はふたたび自分の空腹を満たす行為に没頭した。 † その夜も、舞は旧校舎の廊下に立って、気配を探っていた。 剣を下段に構えながら、その表面を月の光に照らす。それはひとつの儀式だった。この剣は尖ってはいるけれど、刃は焼き込まれていない。だから、力任せに引きちぎることは別段、物を切ることはできない。だが、魔物を斬ることはできた。そして、それを月にかざして光を帯びさせることは、舞にとっては精神的な意味をもつ行為であった。無垢に輝く剣に青い光をまとわせる。そのことによって、不思議と神経が研ぎ澄まされ、舞はみずからを落ち着かせることができた。 ひとつ失望の溜息をつく。今日は何の気配も感じられない。昨夜までに致命的な傷を負わせていたのだから、それが治るまでは姿を現すことはないだろう。今までもそうだった。あとすこしというところまで追い込みながら逃げられ、充分に傷が治ったところで魔物は姿を現すのだ。舞はまだ魔物を一つも斃したことはなかった。 不意に魔物のものではない気配を感じて、廊下の奥を見た。 祐一だった。 「あ、やっぱりいたんだな」 舞と目が合って、しらじらしく驚いている。本当に驚いているのなら、やっぱりなどとは言わない。 憮然として舞は祐一を見据えた。昨夜は祐一が現れた背後に魔物が出現した。それを警戒してのことだった。 「……どうして、ここに?」 「今日も忘れ物だ」 「……嘘」 「鋭いな」 「祐一は嘘つき」 「お互い様だ。今朝は知らんぷりされたからな」 「私は何も言ってない」 「沈黙も嘘のひとつだぞ。まあ、そんなことはどうでもいいや。それよりも……」 急に祐一は真剣な顔を見せ、周囲に気を配りながら、小声で言った。 「今日は来てないのか、魔物」 「うん、いない」 何の気なしにそう答えてから、舞は気づいた。 自分はいま、この少年に、魔物のことについて、素直に答えてしまっていた。 「そうか……」 そうつぶやいたきり、祐一もあたりを見回している。それは魔物を察知する行動としては無意味に近い行為だ。でも……それでも、この少年は、舞の行為に真摯に向き合ってくれている。 「……あのさ、舞」 背中を見せたまま、祐一は尋ねてきた。 「なに?」 「俺、ここにいたら、足手まといか?」 舞は首を横に振った。振った後でそれと気づいて、言い直した。 「ううん。でも、祐一に魔物は見えない」 「ああ、そうだな……囮でもやろうか?」 「おとり?」 肩越しに視線を向ける。すこし思案して、答えた。 「……それなら、いてもかまわない」 「ありがとう。まあ、できれば楽な役がいいんだけどな」 そう言って、祐一はいたずらっぽく笑った。 舞は不思議な気持ちを抱いた。どうしてなのか、この少年はこの世界にいることを、嫌とは思わなかった。それをどう表していいのかわからず、困惑を無表情で塗り込めて、剣をじっと見つめたのだった。 |
| 掲載されている分量は、全体の1/8です。 |